ご注意
*ラブコメですが、タイトル通り死ネタ風・シリアス要素を含みますのでご注意ください。
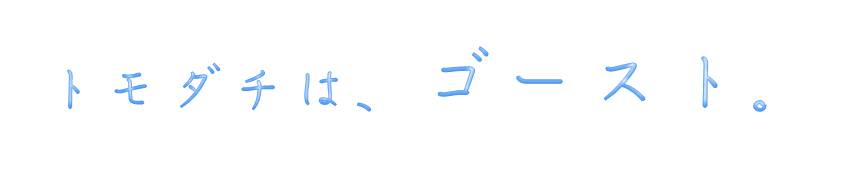
おまえ、今――生きてるって顔してる。
5.友人Kの証言
「最近、ザックスが連れないのよ。カンセル、貴方なにか知らない?」
酒でも女でもなく、ただ友人を探す目的でオーセンティックBARを訪れたカンセルは、「おや」と片眉をあげた。
目的の人物がいなかったからと言って、何も注文せずに退店するには気がひける――
と、スコッチを一人であおっていると。華やかな美人が3,4人、カンセルの周りに集まってきたのだ。
客観的に見て、これはハーレムというべき状況。
そんな風に単純に喜べないのは、その女性たちがカンセル好みの清廉な女ではなく、派手で露出の高い女ばかりであったから――という理由だけではない。
彼女たちの目的が、カンセルと酒を飲むことではなく、カンセルの友人でここにはいない男「ザックス」目当てなのだと、早々に悟ったからである。
「最近、全然お店に顔出さないし。」
「電話しても曖昧な返事ばかりで、つれないのよね。」
どうりで最近習慣のように通っていたクラブにも、行きつけであるこのBAR にも、姿が見当らないわけだ。
遊び歩くなと苦言を呈したのはカンセルだけれど、あの男がすんなり言うことを聞くとは思っていない。
どうせまた夜になれば酒に溺れて、女にかまけて、堕落しているに違いないと――
見つけ出してガツンと説教でもしてやろうと思っていたのだ。それなのに。
「最後に見たのは一週間前、『Loveless time』でだったけど…彼、10時前に急いで帰って行ったのよ。あれ、絶対女がいると思うのよね。」
ねえ、だからカンセルは何か知らない?
そう身を乗り出す勢いで美女たちに問われて、カンセルはさり気なく後ずさりした。
最近のいわゆる〝肉食系〟の女達はどうも苦手だ。控え目で清廉で、照れやなやまとなでしこというものは、ここミッドガルでは絶滅してしまったのだろうか。
「いや、俺もあいつのこと探して店に来たんだよ。俺、ここ一週間、遠征に行ってたからさ。」
だから、ザックスとは連絡とっていなかったんだ、と。そう説明すると、女達はわかりやすく落胆する。
「あーあ、どっかの商売女に、先こされちゃったのね。せっかく彼とデキ婚狙ってたのに。」
「ちょっと!もしかしてアンタ、穴あけてヤったの?」
「残念ながら、針で小さく穴を開けたのがばれてたみたい。彼ったら自分のポケットから新品取り出したのよ。俺はまだパパになる勇気ないから、とか言ってさー。本当信じられない。」
「ソルジャーって恐い!どんだけ目がいいわけ!」
(いやいやいや、恐いのはソルジャーの視力じゃなくて、君たち女のしたたかさでしょ!)
自業自得とはいえ、あまりに強欲で傲慢な女達に狙われていたザックスには、さすがに同情を禁じ得ない。
まだグラス半分は残っているスコッチの名門をテーブルに放置して、カンセルはそそくさと店を後にした。
このまま彼女達と酒をともにすれば、自分もいつ食われてしまうかもわからない。人類としての防衛本能に従い、ここは逃げるが勝ちである。
…悲しいかな、やまとなでしこも天使も、この町ではやはり絶滅してしまったのだ。
――それにしても。
彼女達の言っていたことは気になる。
〝10時前には帰って行ったのよ。あれ、絶対女がいると思うのよね。〟
カンセルがミッドガルを不在にしていた、わずか1,2週間ばかりの間に。
ザックスに恋人が出来ただなんて、にわかには信じられない。
だって、今のザックスは「ザックスじゃない」のだ。
どれだけ美味い酒を飲んでも少しも楽しそうじゃないし。どれだけの女に囲まれても、誰のことも慈しんでいない。自分自身のことを、大事にしていない。
ひと月以上前に、ウータイの戦場で、大きな怪我を負ってから―――
体の傷は癒えても、心の罅はいっそう深くなっている。
…それはきっと、何かの弾みで、簡単に砕けてしまいそうなぐらいに。
ザックス=フェアがどんな男であるか、同期入社かつ友人であるカンセルはよく知っていた。
どこにいたってムードメイカーで、奔放で、天真爛漫。自信に満ち溢れた強い男だと思っていた。
話をするときに、絶対に目を反らさない潔さが格好いいと思っていた。
友人だけれど、男として…尊敬していた。本人には絶対に伝えることはないけれど。
だが、カンセルや周囲の者たちの期待は大きく外れ――実際のところ、ザックスは弱かった。
小さな犠牲を許せない、とても優しい男だった。
***************
8番街の噴水広場にほど近い、大型書店。
そこで用を済ませたカンセルは、遅い昼食をとろうと適当な店を探していた。
コーヒーと焼きたてのベーカリーの香り――それに思わず足を止めると、洒落たオープンカフェがなかなかの賑わいをみせている。
入口に立てられた黒板メニューを覗いただけでも、なかなか美味そうなメニュー展開だ。
立地的に多少値段設定は高めだが、たまには贅沢もいいだろう。
何よりも、ちょうど先ほど買ったばかりの小説を早く読みたいと思っていたのだ。
青空の下で、うまいコーヒーと読書。その誘惑に従い、さらに一歩踏み出したカンセルであったが、残念ながら2歩目を踏み出すことは出来なかった。
(…うわ、見事に女ばっかじゃねえか。)
ランチというよりはアフターヌンティに近い時間だからか、もともと女性受けするスイーツメニューが中心だからか。客層は皆、お喋りを楽しむ若い女性たちばかりである。
流石に、この中入る勇気はない。
色男の友人であればなんの抵抗も無しに入っていって、コーヒーを頼むついでに美人な店員さんのメールアドレスもちゃっかりゲットしてしまうだろうが――
と、今の時間帯は二日酔いでベッドに沈んでいるだろう友人。彼のことを思い浮かべた、その時だった。
「ねえねえ!あのひと、超かっこよくない?!」
「三段もあるデザートプレート頼んでたよ!なんか可愛い~」
「やっぱり彼女と待ち合わせかな?すごいニコニコしてるし。」
「でもずっと一人でいるよ。あんなイケメン待たせるとか、彼女何様?ってかんじ。」
オープンテラスでお茶をしている女性たち――ひとつのグループだけではなく、おそらくはほとんどの女性客達が注目をしているハンサムな男。
それはカンセルが良く知る人物。他でもなく…今、まさに考えていた件の友人、ザックス本人である。
若い女性たちに騒がれながらも、誰を口説くこともなく。たった一人で、コーヒーカップに口を付けている。
女を口説くのが礼儀か挨拶だと思っているような、女タラシが、である。
それだけならまだいいが、彼の目の前には色とりどりのデザートが乗った、三段のアフターヌーンティスタンド。
コーヒーに合うからとビターチョコレートぐらいは食べるようだが、彼はたしか、甘いものは好まないはず。
そして、何よりも不可解なのは。
(…おまえのそんな笑顔、久しぶりに見るぞ。)
何がそんなに楽しいのか、彼は一人で座っているにも関わらず顔を破顔させて笑っている。
電話かメールをしているのだろうか。それとも、誰かを想って笑みを抑えきれないのか。
**************
「ザックス!おまえ、超目立ってるけど。独りで何やってんの?」
ザックスのテーブルを覗き込むけれど、別にスマートフォンをいじっているわけではないようだ。
「おう、偶然だな」と普通に返すザックスからは、最後にクラブで見た時のような荒んだ空気は無くなっていた。
「何って、コーヒー飲んでんだよ。ここの、結構美味いぞ。」
「待ち合わせ、してんじゃないのか。」
「いや?してない。」
即答だったので、それならばと同席を提案するが――ザックスはすぐには頷かない。
「どうする?ああ、こいつ俺と同じソルジャーで、カンセルっていうんだけど……そうか?悪いな。」
ぶつぶつと呟いてから、座っていいとの了承が出る。
その時点で違和感が在ったものの、とりあえず腰を落ち着かせようと、ザックスの対面にあるイスを引いた。
「おい!そこに座んなよ!」
急にザックスが立ち上がったので、何事かと面食らってしまう。
「今おまえ、座っていいって言わなかったか?」
「言ったけど、その席は駄目に決まってんだろ!」
何で駄目なのかわからない。むしろ、バランスを考えればそこが一番自然に思えるのだが。
だが、どうあっても座らせてもらえる気配はないので、その隣のイスを引く。
「カンセルおまえ、なにちゃっかりクラウドの隣に座ってんだよ。」
クラウドって誰だ。というか、その席も駄目なのか。なんだかよくわからないが、ザックスが拗ねている。
「じゃあ、どこならいいんだよ。」
「こっち。」
こっち、と指すのはザックスの隣のイスだ。
しかし、それはおかしい。
四席座ることが出来るテーブルに、男二人が仲良く隣り合って座っているなんて――
女子同士ならばまだあるかもしれないが、自分たちは男だ。しかも軍人で、なかなかに体格がいい筋肉男が二人。
周囲の女の子たちから、ゲイ認定されるのは必至である。
「なんで隣なんだよ。バランスおかしいだろ。しかも狭いし。」
当然の不満を言うと、ザックスは立ち上がり、自分の席をカンセルに譲る。
そしてその対面の「隣」へと、ご丁寧に彼は移動した。
この時点でもう、違和感しかなかったので、最大の謎を問うてみる。
「…で、その三段の豪華デザートは、誰が食うわけ?おまえ、こういうの嫌いだっただろ。」
「別に誰も食わねえけど。クラウドが、菓子の匂い好きだって言うから。」
「さっきからおまえが言ってるクラウドって、誰だよ。彼女か?まあいいや、誰も食わねえなら一個くれ。」
彼女と待ち合わせでもして、珍しくすっぽかされたのかと。適当な推理をしてみる。
「やだよ。」
「なんで!」
「だってクラが………え?もういいのか?まあ、そうだけど。わかったよ、」
「………、」
「カンセル、食っていいって。」
「………。」
違和感なんてレベルじゃない。
なんだこれは。さっきからあえて流してきたけれど、どう考えたって、これは。
「ザックス、おまえ…誰と話してんだよ?」
どう考えたって、ザックスは誰かと会話をしている。
カンセルには見えない、いや、誰にも見えない〝何か得体の知れないもの〟と話をしている。
「やっぱカンセルにも見えないのか。眼鏡かけてるくせに。」
「おい、これはオシャレ眼鏡だっつーの。スコープでもスカウターでもねえんだよ!」
「いや、実はさ。カンセルだから言うけど―――、」
彼に何が起きたのだろうか。
昼間から酒を飲んでいるのか。それとも、まさかついにドラッグに手を出してしまったのか――
背に冷たい汗が伝っていくのを感じながら、カンセルはザックスの続く言葉を待っていた。
「――でさ、クラウドはキラキラした金髪で、子猫みたいにでけえ目で、肌が透き通っちまいそうでさ!
女の子より睫毛長いし、女の子より細腰だし、女の子より甘くていい匂いするんだよ!でも性格は男前っての?
普通なら動揺してびびるような状況でも、冷静に状況判断が出来てすげえと思う。何より肝が据わってる。
そういうとこマジでかっこいいよ。ぶは、おい、照れんなって。まあこんなかんじでツンツンすましてるんだけど、
それもこいつなりの照れ隠しってやつだと思うんだよね。図星だろ?しかも、実はすげえ母ちゃん想いで優しいとこあってさ。
とにかくいいやつなんだよ、クラウドは。」
「ザックス、ちょっとタンマ。」
「なに?」
「さっきからおまえ、クラウド可愛いとかクラウドかっこいいとかクラウド優しいとかクラウドいい匂いとか言ってるけど、」
「うん。」
「だから、そのクラウドって誰なんだよ!」
ザックスはああ、とようやく思い至ったように自分の隣を指さした。
「改めて紹介するわ!こいつ、俺のトモダチの幽霊――クラウド!!」
…もはや、どこから突っ込めばいいのかわからない。
*********
要するに、だ。ザックスの主観を抜きにして話をまとめると、こういうことだと思う。
「つまり、前の住民が化けて出てきて、おまえに憑りついてるってことか。」
「違えよ!別に憑りつかれてなんかねえ。今日だって、むしろ俺がクラウドを連れ出したんだよ!」
カンセルの物言いに不満を感じているのだろう。
ザックスはわかりやすく眉間に皺を寄せる。
たった10日ばかりの間で、ずいぶん親しくなったものだ。得体のしれない幽霊とやらと。
――きっと、よほど心が不安定になっているのだろう。
「いちおう確認だけど。酒もドラッグも、やってないんだな?」
「は?やってねーよ。」
「…それなら、悪いことは言わない。いい医者を知っているから、一度カウンセリングを受けた方がいい。
なんなら、俺も付き添うし。」
「なに、どういう意味?」
カンセルの言葉をすぐには理解しないザックスは、つまり〝その可能性〟を欠片も考えていないということだ。
彼は、本気で信じている。彼の隣の席に、死んだはずの少年が座っていること。
――それが現実だと、少しも疑っていないのだ。
「あのな、ザックス。心ってのは、自分が思うよりもずっと繊細なものなんだ。」
言葉を選びながら、慎重に、ゆっくりと。諭すように続ける。
「おまえが特別弱いわけじゃない。誰だって同じだ。あんなことがあれば、たぶん誰だって気を病むよ。
あるわけないものが見えることだってある。実際、俺だって夢に死んだ同僚が出てきたことが」
「ふざけんなよ。」
怒鳴るでもない、喚くわけでもない。
静かな声だけれど、ひやり、と一瞬で場の空気が凍るような――酷く冷たいそれだった。
「クラウドがあるわけないもの?そんなわけがない。こいつは、ここにいるんだよ。俺の隣に、今だって。」
「おまえがそう思いたいのはわかるけど…冷静に考えてみろよ。なんでそいつは、他の誰にも見えない?
なんで、おまえだけが見えるんだ?」
「そんなん知らねえよ。俺だっていきなり見えるようになったんだ。」
「その子はおまえが〝見たいから〟見えてる。そう思わないか。」
「何が言いたい、」
「クラウドなんてやつはいない。…おまえが作り出した空想だよ。」
どう言葉を選んだところで、ザックスにとっては穏やかでない事実だろう。
それでも言わずにはいられなかったのは、他意はなくただこの友人のことが心配だからだ。
心の病に立ち向かうには、まずその心の傷を自覚しなくてはいけない。そうカンセルは思うのだ。
「……わかったよ、カンセル。」
「ザックス、きつい言い方して悪い。明日にでもおまえの都合がつけば、例の医者を紹介するよ、」
「そうじゃねえ。おまえが信じないってことはわかった。もういいよ。」
「ザックスおまえ、いい加減にしろよ!」
「それはこっちの台詞だ!」
バキン、とザックスの握るコーヒーカップの取っ手が割れた。
「これ以上こいつの前で、〝いない〟なんて言ってみろ。
こいつを泣かすやつは、いくらカンセルだからって――容赦しねえぞ。」
怒りと軽蔑、それら負の感情を言葉にしているけれど。
それでもザックスの瞳には、どこか温度を感じる。護りたいものがあると、その瞳が言っている。
ザックスの右手は宙を舞い、すぐ隣でふわりと揺れた。
怒りにまかせてカップを割ったばかりの指が、今度は酷く優しい手つきで「誰か」を慰めているのだ。
「行こうか、クラウド。」
酷く優しい声で、ザックスが語りかける相手。
どんなに目を凝らしても、それはやっぱりカンセルには見ることが叶わない。
見えないけれど、もしも、もしも本当に――そこに何かが…誰かが、いるのだとしたら。
これまでカンセルは人生において、眼に見えるものしか信じてこなかった。
けれど、一生に一度ぐらいは。
視覚や常識、自分が信じていた価値観よりも…友人のことを信じてやってもいいんじゃないか?
「…しょうがねえな。」
小さくなっていく友人の後ろ姿を眺めながら、自分の中でひとつのことを決意する。
「俺だけはおまえの言うこと、信じてやるよ。――ダチだかんな。」
ぽつり、呟いた独り言は雑踏に消えていく。
遠くの方で、ザックスが振り向いた。
「おーい、クラウド!なにカンセルにくっついてんだよ。置いてっちまうぞ!」
カンセルの座るこのテーブルに、まだ〝その子〟はいたのか。
離れた場所で〝その子〟を待っているらしいザックスは、しばらくの間その場で立ち留まっていたけれど。
数十秒後、今度はカンセルに向かって手を振った。
「サンキューカンセル!おまえなら、絶対信じてくれると思ってた!」
カンセルの呟きを、ザックスに伝えたその子――〝クラウド〟の存在を、疑う余地はもうなかった。
*************
時は、ひと月ほど前に遡る。
カンセルの特技は、いわずと知れた情報の入手・管理である――
調べようと思えばそれはとても容易なことだったし、実際調べるか否かザックスに問うたのだ。
でも、それをしなかったのは、「あのとき」ザックスが望まなかったからだ。
…知りたくないと、ザックスは言った。
名前も、ヘルメットの下の素顔も、年齢も、階級も。〝最期の言葉〟が何であったかも。
それらを背負っては生きられないと、忘れたいとザックスは断ったのだ。
カンセルもそれが正しい選択だと思った。
これまでだって、救えない命はたくさんあったのだ。奪ってきた命もまた数えきれない。
ひと一人の命にこだわっていては、小さな犠牲を嘆いていては、悲しい過去を引きずっていては…軍人は務まらない。
忘れた方がいいと思ったのだ。可能な限り身を軽くして、なんとか生きていってほしかった。
…けれども、結局のところザックスは、自分を許すことをしなかった。
自分で自分に罰を与えてしまった――
自らの頭を拳銃で、撃ち抜いたのだ。
結局死ねなかったと、病室で自分を嘲笑うザックスの表情を、きっとカンセルは一生忘れることが出来ないだろう。
彼が銀の弾で撃ち抜いたのは、脳ではない。
きっと「心」の方だったのだと――そう思うほどに、別人のように乾いた笑みだった。
〝なんで…俺なんか、助けたんだよ。〟
あのとき、ベッドの上でザックスがそう責めたのは。
病院に彼を担ぎ込んだカンセルや、治療を施した医師達に対してではない。
〝俺なんか、助ける価値ねえのに。本当、馬鹿なやつ。〟
病院のベッドの上にいても、彼の心はいまだ戦場にいるのだ。あの日の戦場で、時が止まっている。
〝あんな小さい体でさ、俺の前に飛び出してきて、代わりに蜂の巣にされちまって。〟
あの日から、彼が悔いていることはひとつ。
〝死にたくないって言いながら…あっけなく、死んじまった。俺のせいで。いや、そうじゃない。〟
あの日から、彼が許されたい相手はひとり。
〝俺が、あの子を殺したんだ…………〟
戦場で、身を挺して仲間を護り、その若い命を落とした「顔も名前も知らぬ一般兵」――
ザックスはただ彼だけに、その罪を許されたいのだ。
(2016.05.24 C-brand/ MOCOCO)