ご注意
*映画「恋人はゴースト」のザックラパロディですが、設定や世界観は普通にFF7CC時代です。
パロというかオマージュ。ほとんど映画に関係ないかも。
*ザックスとモブ女の「男女の絡み」が多少ありますので、苦手な方はご注意ください。ザックスが女の敵です、すみません。
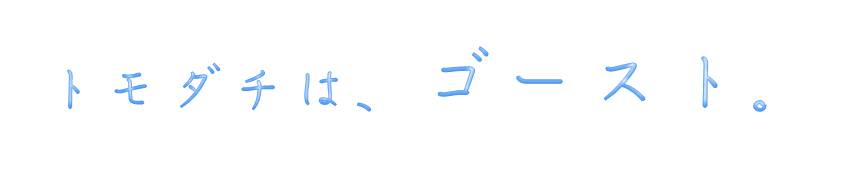
その無念は、
キミがこの世界に愛された証。
2.生きたがりと、死にたがり
たぶん、飲みすぎたのだ。
もうだいぶ日が高くなってきた頃、ようやく床に足をつけたザックスはそう結論づけた。
目覚めた部屋は甘い香りのする小さな寝室だったから、昨夜女の子たちとクラブで酒を飲み、
カンセルに言われるがままこの寮へと訪れた…というところまでは間違いない。
だがその後おきた「非現実的」なこと――
可愛い金髪の少年兵が突然現れ喧嘩をふっかけてきて、しかしその体は透き通っていて、本人は死んだ事実を受け止めきれずはらはらと涙を流していた、なんて。
あれは夢だったのだ。そうに決まっている。
ありえない、とわかってはいるけれども。いちおう部屋の中を捜索してみる。
隣の寝室、リビング、風呂場やトイレ、ベランダ、クローゼットの中。
冷蔵庫や鍋のフタまで開けてみたところで、馬鹿馬鹿しい、とため息をつく。
「…幽霊なんて、いるわけねえっての。」
もともとザックスは、リアリストである。
もしもこの世に幽霊がいるとして、死んだ者が未練や悔恨の念から彷徨っているのだとしたら。彼らがこれまで、ザックスの前に現れなかったわけがない。
戦場でたくさんの仲間の死をみてきた。見捨てざるを得ない命があった。敵兵を手にかけてきた。
彼らが全て幽霊になったのだとしたら、恨みつらみを叫びながらさぞやザックスを苦しめることだろう。
だがそんなことは現実にない。
死んでしまえばただの屍。
霊魂や霊体、天国や地獄、生まれ変わりや輪廻転生などといったものは、宗教上の信仰、あるいは映画や本の中のストーリーである。
ザックスにとって、リアリストであることは――軍人である以上は欠くことのできぬ価値観、といえるのだ。
********
兵寮の規則は厳しい。
門限や消灯時間、あまつシャワーの利用時間までも定められているし、ペット禁止、アルコール禁止、喫煙禁止、賭博禁止。外部の者を連れ込むのも禁止である。
不定期に寮監による見回りがあり、生活態度や持ち物の検査が行われるために気が抜けない。
しかし、寮監は上級曹長の職務である。
大将クラスの軍位をもつザックスに対して、少しの発言権も抑制力も持ち合わせていない。それが現実だ。
「サー…あの、寮は女人禁制でありまして………」
「大目にみてよ、俺は一般兵じゃないしさ。起床時間より前にちゃんと帰すし、他のやつらに見られたりしないし!」
「し、しかし…」
「おまえ、マックスって言ったっけ?今度飲みに連れてってやるから見逃して?ね?」
「は、はあ……」
「もちろん可愛い女の子つき!」
「!!イエス・サー!!」
前回はカンセルの不興を買ってしまったために、お持ち帰りが出来なかった巨乳美女…を連れて、ザックスは堂々と寮の廊下を歩く。
居合わせた寮監が引き留めようとするも、形ばかりの抑止であって、すぐに「見ないふり」をしてくれるのだ。
軍とは典型的なピラミッドを描く、身分社会である。
「神羅軍の寮にこっそり入るなんて、ドキドキする!」
「刺激的だろ?声を殺してエッチするのもさ。」
古びたアンティーク・キーを回し、707号室のドアを開けた瞬間。早急に女の服に手をかける。
お互いそれなりの飲酒をしていて酔っているし、今さら愛の言葉やらムード作りは面倒というのが本音だ。
それに、多少強引な方が「情熱的」な行為だと――愛を錯覚するのが女という生き物。
服を脱がしながら、左側の寝室へと入っていく。ふわりと、例の甘い匂いが微かに香った…ような気がした。
「このベッド…ザックスには、ちょっと小さいんじゃない?」
「そうだなあ。あんまり激しく動くと、落ちちゃうかもね。」
酔いにまかせて少し乱暴に、相手の女をベッドへと押し倒した。
自らランジェリーを脱いだ女は、少しの恥じらいも躊躇もなくザックスに足を広げる。
着けなくて大丈夫だと挿入を促す言葉をやんわりといなして、尻ポケットからコンドームを取り出した。
この年頃の女に、避妊なしのセックスは危険だ。
「今日は安全日だから」「ピルを飲んでいるから」などという女の言葉は、男の「先っちょだけだから」と同じぐらい信用が出来ない。
経済力と顔面偏差値の高い男を、いかにして手に入れるか…その機会を狙っている狡猾な女は少なくないのだ。
(…うーん。美人だし、いいカラダ、してんだけどなあ…なんか違うっていうか、)
化粧は濃い目だが、それが似合う華やかな美人。ブラジャーを外してもちゃんとボリュームのある胸。
ムードや前戯などといった面倒な段階を踏むことを求めず、積極的に足を開いてくれている。
さぞや自分の体と、テクニックに自信があるのだろう。
こういう性に積極的な女を、これまでザックスは好んで選んできたたはずなのに。それなのに、
(何か足りない…気がする。)
彼女に足りないものはなんだろう。
いまいち興奮しきれないせいで、自らの右手で数回扱いてからコンドームを装着する。
まるでAVのように足を広げて入れてほしいと強請る女――男が喜ぶと思っているらしい――の脚を抱えた時でさえも、ザックスの感情はどこか冷えていた。
何かが違う。何か違和感。何かひとつ、たったひとつなのだけれど興奮できない要素がある。それは、
(―――匂い、だ。)
女のつけている香水の匂い。それに、服を脱いだらわかるひとの体臭。キスをすれば嫌でも感じる唾液の臭い。それらが、ザックスの嫌悪を呼んでいる。
何故ならその女の持つ臭いは――あまりにこの部屋に相応しくないからだ。
「…今更、なんだけどさ、」
「ん、なあに?ザックス。」
「シャワーとか…浴びてからにする?」
「……………………え?」
しまった――と、自分の失言に後悔するも、手遅れである。
女は酷く驚き、そうしてすぐに顔色を変えていく。彼女の顔が、怒りと羞恥で真っ赤に染まるのも当然。
生まれたままの姿で、足を開いている彼女――ザックスはその恥部を前にして、まるで不浄で触れないと拒否したようなものだからだ。
「…………く、臭いってこと?」
「違う!違うって!…えーっと、なんだ、俺ってちょっと潔癖でさ。エッチの前はシャワー浴びる派っていうか、」
「つまり、汚くて触りたくないってこと?」
「違う違う!やっぱり臭いとかすると集中できないじゃん?ぱーっとシャワー浴びてからのがいいかなって、」
「全然、違くないじゃない。」
まずい。繕おうとすればするほど、失言が増えていくだけだ。
女性に恥をかかせてしまった今、この後に待っているのは平手打ちか、泣き狂いか、スマホ水没の仕打ちか――きっと、ろくな事態は待っていない。
「ごめんごめん!全部嘘。…キミがあんまり魅力的だったから、俺、柄にもなく緊張しちゃってさ。」
女を敵に回して勝てるわけがない。面倒事は避けるが吉だ。
ワントーン落とした低い声で囁いてみせれば、場の空気はすぐに性的なものへと戻っていく。
「それなら、いいけど。焦らすのも大概にして。」
「了解。」
とにかく、適当に挿れて出してしまえば、相手は満足するのだ。
臭いが好みじゃないなどという事実は、あまり鼻呼吸をしなければいいだけのこと。
――と、だいぶ失礼なことを考えながら、再度女の脚を割り開いた。
ゴム越しに、彼女の秘部へとそれを宛がった…まさに、その時だった。
ふわ、と。甘い甘い香りがザックスの鼻腔を擽る。
むろん、女から香るのではない。ピローやベッドシーツから香るのではない。
花や蜜のように甘く、石鹸のように清らかで、果実のように爽やかな。なんだかどうしようもなく、男の本能をざわめかせるような。
この香りはいったいどこから――すぐ近くから、香っているような気がするのに。
「あれ?本当、すっげー近くから………香ってる?」
「ちょっと!早く挿れなさいよ!!!」
宛がわれたままその先に進もうとしないザックスに、痺れを切らして女が喚く。
だけどもう、彼女を気遣う余裕などなかった。
何故なら、ミルキーブルーのベッドシーツに散らばる栗色の巻髪、そのすぐ隣に。きらきら、と繊細に煌めく金色の糸がある。
ピローを掴む女の指は、真っ赤に塗られたネイルが毒々しいほどであるが、そのすぐ隣に。清潔に整えられた薄桃色の爪と、白魚のごとくしなやかな指がある。
睫毛エクステだか付け睫毛だか、繊維たっぷりのマスカラだかは知らないが、とにかく人工的に盛られた女のそれとは違い――髪色と同じ金が眩い、天然でふさふさと音をたてそうなほどに長い睫毛。
打算や駆け引き、狡猾さを語る女の瞳ではなく――生まれたての赤子のような、子猫のような。邪心や汚れを知らぬと語る、美しいまでに澄んだアイスブルーの瞳。
―――と、目が合った。
「うわああああああああああああ!!!!」
「ぎゃああああああああああああ!!!!」
思わず、ベッドから飛びのいて、勢いのまま床へと落下する。これはデジャブだ。
「ひ、ひひひひとのベッドでなにやってるんだ!!!」
そう、昨夜とまったく同じ…応酬である。
「いやいやいや、ここは俺の部屋だから!オマエこそ、なに人様の濡れ場を覗いてんだよ!」
「の、覗いてなんかない!馬鹿を言うな!俺が寝てるところに、アンタが勝手に女を連れ込んだんだろ!」
「だったらもっと早く言えよ!なんで黙って寝てんだよ!!」
「いきなりおっぱじめるから、こっちだって動けなかったんだよ!!」
ぎゃあぎゃあと言い争う様を、女は足を広げたまま眉を顰めて見ていた。
その姿を改めて認識したらしい少年は、思い切り顔を背けるともごもごとザックスに指示をする。
「と、とにかく……そのひとに、何かかけてあげて。あ、アンタも前ぐらい隠せよ!!バカ!変態!」
なんだ、男のくせにこの恥らいっぷりは。
こんな耳まで真っ赤に染めていては、彼の悪態さえも結局は照れ隠しとイコールなのだとわかる。
いまだに足を閉じようともしない、羞恥を知らぬ女とのこの差はなんだ。
「ザックス…あなた、誰と喋ってるの?」
「あ、こいつ、たしかクラウドっていって。たぶん、前にこの部屋に住んでたみたいなんだけど、」
「こいつ?」
彼女はキョロキョロと辺りを見回すが、少年のの姿を捕らえることは無い。
まるで見えていないかのように。いや――実際、見えていないのだ。
(…あ、そういえば。こいつってもう、)
あまりに活き活き(?)と言い争ってしまったものだから。すっかり大事なことを失念していた。
昨夜の出来事が夢でないというなら、少年の体は触れることが叶わぬもの。
つまりもう、この世には。
「運悪く死んじまったみたいでさ。まだ少年兵だってのに――可哀想な話なんだけど、」
この世にはいない者。いや、実際はここにいるのだから、「いていい存在ではない者」だろうか。
魂や霊体、死後の世界などというものを、全く信じてこなかったザックスであるが、こうして体験してしまえば否定しようもない。
少年の体が透き通るのは事実だし、彼女には見えぬというならばなおのこと。
何故ザックスに見えて彼女に見えないのか、他の者には果たしてどうなのかは知らないが――。
だが今のところ、事実だけをもとに察するならば、彼が「幽霊」の類であるという可能性は高い。あくまで、可能性の域だけれど。
世間話のように、なんてことでもないという風に。
そこに罪悪感を伴うこともなく、事実と思われることを口にした。
「死んじまったみたいでさ」というその言葉を、女は信じることはない。見えていないのだから当然かもしれない。
ザックスの虚言だと捉えた彼女は、こちらの想像通りのリアクションをとる。
「勃たないからって馬鹿じゃない?!私に魅力がないんじゃない、アンタのそれが役立たずなのよ!」
これでもかという、遠慮のない平手打ちをザックスに喰らわせてから、部屋を出て行った。
平手打ちなら結構だ。
女性のヒステリーでスマホを割られたり、水没させられるよりだいぶマシだから。
と、わりと冷静に彼女を見送る。長いネイルがついでに頬をひっかいたのか、ひりひりと痛む左頬をさすりながら。
そこで漸くして、気付いたのだった。
――酷く傷ついた表情で立ち竦む、少年のことを。
(俺、さらっと何言ってんだよ!)
先ほど彼を前にして、言ってはいけない台詞を口にしてしまったこと、彼を傷つけてしまったこと。
「死んじまったみたいでさ」なんて――――言われた方はどんなにショックを受けるだろう。
「えっと……、クラウド、だよな?俺デリカシーないってよく言われるんだ。ごめん。ほんと、ごめんな。」
「…………………別に、どうでも。なんとも思ってないし。」
「じゃあ、仲直りしてくれる?」
「仲直りって……なにそれ、子供みたい。そもそも、トモダチでもなんでもないし。」
悲しそうなそれから、呆れたような表情に変わっていく。
「じゃあ、トモダチになろうぜ。今この瞬間から、友情成立ってことで!」
「別に……どうでも、いいけど、」
「けど?けどけど?」
「いい加減、そのフルチン隠せってば!」
呆れた表情から、困ったような笑みに変わる。
それがどうしようもなく、嬉しかった。
********
――――俺、この世に未練があるんだよ、きっと。
狭いシングルベッドの上で、二人並んで腰掛けながら。ぽつりぽつりと少年――クラウドは胸の内を語った。
生前の記憶が曖昧であると言う彼。
前回のザックスとの言い争いにより、自分の名と軍人であったことは思い出したが、断片的に訓練の記憶が残っているだけで。
ミッションや詳しい職務のこと、家族や故郷、交友関係。全て思い出すことが出来ていないらしい。むろん、自分の「最期」についても。
けれど、記憶が全くないわけではない。
言語や知識はほぼ完全に残っているし、神羅軍やミッドガルについての一般的知識、それに昨今の社会情勢や経済についても知っている。
むしろ低減税率がどうだの、ナベノミクスがどうだのと話すぐらいだから、ザックスよりもよっぽど博識といえるかもしれない。
ただ、クラウドには…「想い出がない」のだ。
何を夢見て、何を好んで、何を嘆いて、何を愛してきたのか――それらを忘れてしまったのだと、彼は言った。
「気付いた時には、この部屋のベッドにいて…目の前に、ザックスがいたんだ。昨夜も、今夜も。」
「それ以外の時間はどこで、何してるんだ?」
「わからない。寝てるのか…そもそも、消えてるのかも、しれないし。自分じゃわからないんだ。」
不安そうに目を伏せる。いつ消えてしまうかもわからぬその不安定な存在、彼の感じる恐怖は当然だった。
「最期の、ときのこと。それがどこだったか、どうしてそうなったかも思い出せないんだけど――
死にたくないって、何度も思った。それだけは、覚えてる。」
クラウドは、小さな拳をぎゅっと握りしめる。
年の頃は15,6歳といったところ。さぞや無念、だったに違いない。
「軍人のくせに、本当、情けないんだけど。」
死を受け入れられぬ自分を、彼は恥じる。
「情けなくねえよ。そんなん当たり前だろ。俺だって今いきなり死んだら、未練タラッタラだよ。」
「アンタも…いえ、サーも、同じ、ですか?」
つい先刻、改めて自己紹介を交わした際に、ザックスの階級とソルジャーである事実を知ったからだろう。
なるべく敬意を持って話そうと、口調を改めようとするクラウドに、ザックスは異議を唱える。
「ザックス!サーじゃなくて、ザックスって呼んで。敬語もなし。」
「でも…」
「さっきまでの、恐いもの知らずで憎ったらしいオマエがいいの。」
「にくったらしい…?いや、そういうわけには、」
「トモダチ、だろ?」
「………………うん、」
控えめに頷くのに満足して、ザックスは彼の頭に手を伸ばした。
それはほとんど無意識だったから、すい、と手がすり抜けてしまったことに少なからず動揺する。
…クラウドの瞳が、また悲しそうに揺れてしまうからだ。
とっさに、彼の頭を撫でる仕草をする。そこに実体は感じられなくて、温度も触感もない。
けれど、それでも撫でてやりたかった。彼の体に、心に、寄り添ってやりたかった。
「なにそれ。」
「ん?クラウドをエアーナデナデしてんの。」
「楽しい?」
「病み付きになりそうだな。」
ばかじゃない、と笑う顔が可愛い。眉を下げているよりもずっといい。
残念だな、と思った。
この子が、もうこの世にいないことが。
この子の追いかけていただろう夢、それらがもう叶わないことが。
両親や友人、同僚、もしかするとガールフレンドもいたかもしれない。それら多くの人々が、この子の死を嘆いたことだろう。
ほんの数分、彼と言葉を交えただけのザックスが、これだけ惜しいと思うのだ。
彼のこれまでの人生、それを知る由はないけれど。
彼は生きるべき人間だった。「向こう側」の人間だったのだ。…自分とは、違って。
「…本当、言うとさ。もし、俺が今死んじゃっても――きっと、幽霊にはなれないよ。」
クラウドはわからないという風に、首を少しかかげた。
こんなことを告白することは、きっとデリカシーに欠けたことで。彼を傷つけてしまわないか、心配になる。
「一生懸命生きて、やりたいことがあって、夢があって。…守りたいものがあって。そういうやつが…きっと、クラウドみたいなやつが、幽霊になるんだよ。
未練があるっていうのは、それだけ人生充実してたってことだろ。ひとに、世界に、必要とされてたってことだ。」
クラウドの大きな瞳が、見開かれていく。
この少年独特の、無垢で曇りのない瞳には、どれだけの可能性が満ちていたのだろう。これだけ綺麗なのだから、想像するに難しくない。
「ザックスは、ソルジャーだろ?将官クラスで、軍の中心で、きっとみんなの目標で…必要とされてるだろ。俺みたいな、下官クラスよりもよっぽど、」
「クラウド、」
きっとおまえ、すごく優しいいい子だったんだな。そう返して、また頭を宙で撫でてやる。
「本当は俺。未練なんか、ないんだ。…ごめんな。」
「え?」
「オマエみたいに、生きたかったやつが死んで。俺みたいなやつが生きてるなんて。ごめんな…」
どれだけ酒を飲んでも味を感じないし、酔うことが出来ない。
毎夜セックスをしても誰のことも慈しめないし、愛の言葉を口にすれば嘘を重ねていくだけだ。
起きている時も、眠っている時も同じ。
一度でも瞼を閉じてしまえば、瞬きひとつしてしまえば、瞼の裏側で「あの日」の記憶がフラッシュバックする。
あの日の悲しみが――追いかけてくる。
この世に未練なんかない。
本当はもう、生きるために呼吸をするのも辛かった。
今日東京で、ザックラが開花したそうですね。(2016.03.21 C-brand/ MOCOCO)