ご注意
*映画「恋人はゴースト」のザックラパロディですが、設定や世界観は普通にFF7CC時代です。
パロというかオマージュ。ほとんど映画に関係ありません。
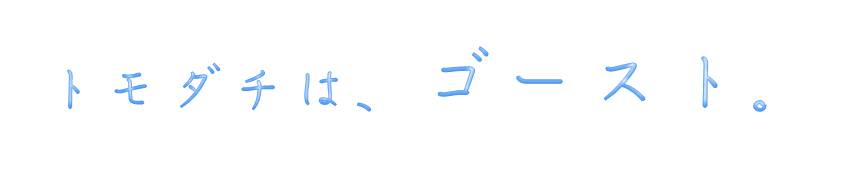
キミを連れ出したつもりだったけど、
救われたのは僕のほう。
3.幽霊と、デート1回!
瞼を閉じるのが、恐かった。
赤く染まる世界。硝煙と鉄の臭い。冷たくなっていく体温。どれだけ叫んでも声が出ない。
助けてくれという声が出ない。―――誰も、助けにきてくれない。
ああ、これはいつもの夢か、と。すぐにわかった。
夢なのだから早く覚めてほしいのに、それが思うようにいかない。
いったいあとどれだけの間、この恐ろしいまでの孤独に耐えねばならないのだろう。
いったいあと何回、この悪夢を見なければいけないのだろう。
いっそもう、終わりにしたい。
次に目が覚めたときには、今度こそこのこめかみに鉄の鉛を打ち込んで―――…
*********
「ザックス!」
「………」
「ザックス!起きろってば!!」
「…………え?」
耳元で自分を呼ぶ声。
怒っているのか、焦っているのか、とにかくしつこく繰り返されるその声の主が、誰であったか。
それの答えを導くまでに少し時間を要した。
昨夜も大量の飲酒をしたせいで、頭痛が酷い。そのせいで頭の回転が鈍っているのだ。
「アンタ、一人で場所とりすぎ。でかい図体のくせに大の字で寝るなよ!俺が潰れるだろバカ!」
ふわり、と甘い風が微かに入り込んできて。ストライプ柄のカーテンが揺れる。
じっとりと全身にかいていた汗が、すうっと引いていく。心地よさに思わず目を細めた。
「ザックス、聞いてんのかよ。…もしかしてアンタ、目を開けたまま寝てる?」
「あ、わりい。そういやオマエ、いたんだっけか。………………いやいやいや、おかしいだろ。やっぱりおかしいだろ!」
「なにが?」
「なんでオマエ、幽霊のくせにまだいるんだよ?!もう朝だぞ?!」
何時かはわからないが、日は完全に昇っている。
幽霊といえば真夜中だったか、丑の刻だったか、とにかく夜におどろおどろしく出没するのがセオリーである。
こんなカーテンから光が差し込む眩しい朝に、まるで故郷の口うるさい母親のように起こしてくるなんて。何かがおかしい。
「幽霊が夜行性って、誰が決めたわけ。」
確かにそうだ。朝型の人がいれば夜型の人もいる。そんなかんじで、朝から活動したい幽霊もいるのかもしれない。
と、ずれた思考を廻らせながら、少年が少し口を尖らせていることに気付く。そういえばこの幽霊は、なんで怒っているんだったか――
「で、クラウド。なんで怒ってるんだっけ?」
「だから!俺のベッドなのに、アンタ占領しすぎだって言ってんの!寝相最悪だし、寝言うるさいし!」
「あ、まじで?ゴメン。」
寝ているのだから不可抗力とはいえ、どうやら寝相や寝言で彼の不興を買ったようだ。
昨夜は、互いの身の上を語り合いながら――気付けば眠っていた。
クラウドにとって、このミルキーブルーのベッドは自分のものであるだろうが、かといってザックスも譲る気はなかった。隣にも同じ間取りの寝室がある。あるけれども、やはりこのベッドがいいのだ。この、匂いがいいのだ。
気付けば頭痛もどこかへいってしまった。なんとも安らげる不思議な香りである。
そんなわけで、どちらもベッドの所有権を主張したまま、結局互いに譲らなかったため。妥協したのか面倒になったのか、結局二人ともこのベッドで寝たのだ。
小さなシングルベッドでは無理がある――というわけでもなく、普通に収まってしまったのは、クラウドがザックスとは違って小柄で華奢であるから。そしてなによりも「幽霊だから」である。
幽霊は実体がない。だから、けっして生きてる人間と触れ合うことはない。
「寝言はともかく、寝相はいいじゃん。クラウドが潰れるわけじゃなし。」
「気分的に嫌だ。その無駄な筋肉がこっちに寄ってくるだけで、恐怖でしかない。」
ああ言えば、こう言う。
この生意気で短気な性格は、生前からなのだろうか。
せっかく顔が天使のように可愛いのだから、もう少し性格の方もどうにかしたらいいのに。もったいない。
「まあいいや、俺、シャワー浴びてくる。なんか、すっげー汗かいたから。」
「………、」
「なに?一緒に入る?」
「……入るか、バカ。」
クラウドが、その子猫のような大きな瞳で、こちらを窺っている。
何か言いたいことがあるのだろうか。
ベッドルームからから出て、ユニットバスへと入っていく。
タンクトップを脱いで、ボクサーパンツ一枚の状態で、まずは髭剃りでもするかと洗面台の鏡を覗いた。
「っておい!いきなり鏡に映るなよ!!びびるだろ!!」
足音も気配もなく、いきなり鏡に映りこんでくるとか怖すぎる。まるで心霊映画のワンシーンだ。
いや、実際に彼は幽霊なのだからこんな登場(?)もしょうがないのか。
「…………、」
「え?なに?マジで一緒にシャワー浴びる?それともションベン?」
「……………違くて、」
「おい、鏡に血文字を書くとかは止めてくれよ?!」
昔、そんな映画を見たことがあった気がする。たしか「kill you」とこてこての血文字で書かれていたのだ。
「…………違う。」
「じゃあ、なに?」
電動シェーバーを顎で軽く滑らせ、髭を剃る。
それでも彼は話そうとしなかったので、そのままボクサーパンツを脱いでバスタブに入った。
水が跳ねないようにとシャワーカーテンを閉じて、シャワーコックを捻る。
もうそこにはいないかな、と。そう思っていると、シャワーの音に紛れて、控え目な声が聞こえてくる。
「……………………何の夢、見たの?」
聞き取り辛く、思い切りカーテンを開けて「え?なに?夢?」と聞き返すと、まだその場に居たらしいクラウドは慌てて後ろを向いた。
積極的な女もいいが、こういううぶな反応も悪くない。むしろ、すごくいい。などと思わずにやけてしまった時。
「すごく、うなされてたから……、」
「え、」
「恐い夢、見たのかなって。」
―――もしかして。
この子が、自分を執拗なぐらい起こしてきたのは、焦った表情で呼んでいたのは。
(俺が、うなされてたから、)
怒ったふりをして。寝相や寝言が煩わしいと文句を言うふりをして。
(起こしてくれたのか。)
何て不器用で、あまのじゃくで、素直じゃなくて、可愛げがなくて。…優しい、子。
「べ、別にどうでもいいけど!」
とっさに興味のないふりをして、バスルームを出ていくクラウドの後ろ姿を見送ると。
ザックスは慌てて体に残ったソープを洗い流し、体を拭くのもそこそこに彼の後を追った。
どうしてだろう、目の届くところにいてくれないと落ち着かない。
*******
食事はいらない、と。彼は首を横にふった。
人間だけじゃなくそれ以外の実体――たとえば、部屋のドアや水道の蛇口、パソコンやボールペンにも触ってみようと試みたが、出来なかったらしい。なのでむろん、食器やマグカップ、焼けたトーストにも触れることが出来ない。
今も彼は、リビングのソファに腰かけることは出来ているが、ソファの弾力やファブリックの質感を感じることは出来ていないらしい。ただ、そこに座っているだけ、ということだ。
「腹、へらねえの?喉も乾かない?マジで?」
深く考えずに、二人分の簡単な朝食を作った後で、彼が食事を要していないことに気付いた。
テーブルの上に並べられたふたつのモーニングプレートを前に、クラウドは眉を下げた。
「ごめん、美味しそうなんだけど………食べられないんだ。」
「俺が勝手に作っちまっただけだから。クラウドが謝ることじゃねえよ。」
クラウドの体型から小食だろうと判断して、もともと少な目の量で作ってある。二人分ぐらいザックス一人でもたいらげることが出来る量だ。
「…それ、すごくいい匂い。なんのジャム?」
「ああこれ、おふくろが送ってきたオレンジのジャム。俺は甘いもんはあんまりなんだけど、オマエはこういうの好きそうだと思ってさ。」
「うん、たぶん。たぶん…好き、だったと思う。」
キツネ色に焼けたトーストに、たっぷり乗せたオレンジのジャム。
故郷のゴンガガはサマーオレンジの名産地で、これは小さい頃からよく知った味である。成長とともに味覚は変わるもので、甘いものはあまり好まなくなったのだが、母親からすればいつまでも息子の好物と思っているのだろう。
たしかに、南国を思わせる爽やかな果実の香りは、悪くないのだけれど――
「あれ?そういえば、おまえ、匂いは感じるんだな。」
ふとわいた疑問を問えば、クラウドも初めてその事実に思い至ったのか、少し考え込んだ後で答える。
「そういえば…温度とか感触とかはないけど、匂いはわかる、気がする。」
「気がする?」
「もしかすると、本当に匂いがわかるんじゃなくて、記憶を錯覚しているのかもしれないし。」
なるほど。確かに、「香り」「匂い」というものは潜在意識の深くに刻まれる記憶になりうるのだと、どこかで聞いたことがあった。
「そういえば、オマエも…」
「俺?」
「触れないし、温度も感じないけど、匂いはする。…気がする。」
「なんかそれ、変態臭いよザックス。」
「ちげえよ!まじで、オマエがそばにくると甘い匂いすんだよ。なんかこう、花みたいな、石鹸みたいな…」
「犬の嗅覚こわい。」
そうザックスを非難しながらも、どこかクラウドは安心したようだった。
誰にも触れられることがない、何にも触ることができない、不安定で不確かな「霊体」という存在。
それでも、匂いというこの世に存在する証拠がちゃんとあるのだ。
「ザックス、トイレに入ったら消臭スプレー使えよ!」
「いや待てクラウド、臭い気がしただけで、それはあくまでおまえの記憶がみせる錯覚かも…」
「ううん、ふつーに臭いから。」
「すいません!!!」
どうやら、彼の嗅覚は生前の記憶をなぞっているだけではなく。実際に機能しているようだ。
********
IDcs999732クラウド=ストライフ一等兵
階級:曹長 (二階級特進後 少尉)
年齢:16歳 軍歴:2年6か月
体重:48,2kg
身長:166,5㎝
生年月日:XX年8月11日
血液型:AB
出身:ニブルヘイム
家族構成:母
「っていうか、オマエ痩せすぎじゃね……?48㎏って、女子じゃん。」
「そこはどうでもいいだろ!」
とりあえず、生前の記憶が曖昧であると言うクラウドのため。
少しでも思い出すきっかけになればと、彼について調べてみることにした。
部屋に据え置いてある神羅の軍用端末で、彼の名を検索すると簡単なプロフィールが出てくる。
死亡日や、死亡したミッションについては――書かれていない。
「オマエ、故郷に母ちゃんがいるのか。」
「……かあさん、か。覚えてないけど、」
「きっとクラウドの母ちゃんなら、すっげえ美人だろうな。オマエとそっくりでさ、金髪碧眼で、色白!」
「俺はきっと、マッチョでごつい父さんに似たんだもん。…覚えてないけど。」
自分が女顔である事実を、認めたくないらしいクラウド。それがあまりに可笑しくて、思わず吹き出してしまう。
客観的に見ればクラウドのその美貌は、誰もが羨む愛らしさだと言うのに。
「ザックス、何笑ってるんだよ!俺はあと1年もすれば身長がいっきに伸びて、筋肉隆々になって、胸毛だって生えてくる予定だったんだ!」
「ちょ…、腹いたい!頼むから、これ以上笑わすなって!」
身長は伸びるだろうし、多少筋肉はついたとしても。この線の細さでは、筋肉隆々になるのは難しいだろう。
胸毛にいたっては、間違いなく無理だ。産毛さえもほとんどないのだから。
何はともあれ、何か記憶のきっかけになるものはないものかと。
二人は部屋の中を捜索することにした。神羅の端末で調べられる程度の情報では、あまりに少なすぎる。
「教本とか辞書とかはそのまんまみたいだけど、さすがに個人的なものはないな。」
「死んじゃったら普通……遺品整理、するもんね。」
クラウドの言葉通り、カーテンやベッドシーツはともかくとして、個人的な衣類や写真などはひとつもない。
ザックスが次の住民としてこの部屋を訪れた以上、当然、遺品整理は終わっていると考えるのが普通だろう。
そのとき、ベッドの下に落ちている赤い宝石のようなものを見つけた。
――女性用のピアスである。
「ひゅー!クラウド君も隅に置けないじゃん!オマエも女、連れ込んでたの?」
「はあ?そんなわけないだろ!それ、アンタの恋人のしていたピアスだろ。」
恋人、という言葉に反応が遅れてしまった。
ただヤる目的で連れ込んだ女性を、恋人、などというカテゴリにいれたことがなかったからだ。
「別に、恋人じゃねえけど。もう二度と会わないだろうし。」
「……連絡、すれば?きっと向こうも、ザックスの電話を待ってるよ。もともと俺のせいであのひと、怒っちゃったようなものだったし、」
申し訳なさそうな顔で気遣ってくれるクラウドの言葉に、彼がいかに清らかな人生を歩んできたかがわかる。
クラウドは、ザックスが恋人と喧嘩をして意地を張っていると思っているのだ。
まさかもともとセックス目的で連れ込んで、朝になったらどのみちサヨナラするつもりだったなどということは、想像だにしていないのだろう。
「そのピアスも、探してるかも…やっぱり、返してあげないと。」
というか、おそらくは。わざと忘れていったのだ。
十中八九、このピアスをきっかけにザックスから連絡をいれさせようとしているのだろう。
「もともとそのピアス、俺が買ってやったやつだからさ。放っておけばいい。」
クラウドには、狡猾で計算高い女の意図することなど、知る由もない。彼女や自分と、クラウド。同じ人間なのに、こうも違うなんて。
「………そういえば、俺、」
「うん?」
「母さんに、ネックレス買おうって、思ってた。」
赤いピアスを見つめながら、呟いたクラウドの言葉。突然のことに驚いた。
「思い出したのか?!」
「それ、見てたら急に……母さんの顔が浮かんで。そういえば、母さんの誕生日にネックレスを買おうとしてたなって。節約して、頑張って金を溜めてたんだ。やっと、母さんを喜ばせてあげられるって、思ったのに―――………」
ザックスが女の機嫌を取ろうとして、ピアスを買ってやったような馬鹿らしい動機ではない。
そのどこまでも真っ直ぐで、優しい彼の「真心」というものに触れて。
どうにかしてやりたい、と単純に思った。
「―――よし!買いに行くぞ!!」
「え?なにを?」
「だから!クラウドの母ちゃんに渡す、誕生日プレゼント!!」
思い立ったが吉日。すぐに財布をつかむと、尻ポケットにつっこんで部屋を出ていく。
「え?今?今から?」
「天気いいし、デート日和じゃん!」
そういえば、日の高いうちに外出するのは、ザックス自身久しぶりだ。
夜になればバーやクラブを遊び歩き、昼は自宅かホテルで惰性に過ごす。そんな虚しい毎日だったから。
*********
そういえば、幽霊でも移動できるものなのか、と。
そんな疑問が頭に浮かんだのは、彼を実際に街へと連れ出してからのことだが、今更である。
バイクの後部座席に乗せたときも、バイクを駐車させて店の前までやってきたときも、彼はきちんと付いて来ていた。
「ここ、なんか高そう……、俺、兵服のままだし、つ、つまみだされちゃうよ。」
ザックスがよく利用している老舗宝石店。女性であれば、誰しも憧れを抱いているだろうブランドだ。
ブラックスーツを着こんだドアマンの存在に気付いた瞬間、クラウドは入店を渋った。
「いや、平気だって。たぶん、見えてないし。」
「………、見えてないんだ。誰も…」
昨夜の女性だけではなく。クラウドのことは、おそらく道行く誰もが見えていないようだった。
「ザックスだけ」が、何故かクラウドを見つけることが出来るというわけだ。
顔見知りのドアマンはザックスに会釈をする。やはりクラウドのことは見えていない。
カウンターごしに声をかけてきた販売員の女性も、クラウドの方を見向きもしなかった。
「クラウドの母ちゃんは、どんなのが好き?」「何色が好き?」「瞳の色は?」「誕生月いつ?」「ハート好き?」
などと、クラウドに質問を重ね続けるザックスを、販売員はいぶかしげに見ている。
「ちょっと…ザックス。他のひとは俺のこと見えてないんだから、ザックスが独り言を言ってる変なやつみたいに思われるだろ。」
「どう思われたっていいじゃん。今は母ちゃんに似合うネックレス探す方が大事!」
「……でも、」
「なあなあ、これは?クラウドの瞳の色とおんなじ、アイスブルーの石!」
「………、」
「クラの母ちゃんも、金髪だろ?絶対似合うと思うぜ。チェーンは、おまえと同じ肌の色なら、ゴールドよりも断然プラチナだな。」
「…………、」
「おお、すげえ!光に透かすと色んな色にかわるんだって。マジでオマエの瞳みたいじゃん!」
「………………ありがとう、ザックス。」
泣きそうな顔で、小さな小さな声で礼を言うクラウドに。
ザックスはにかりと笑い、やはり恥ずかしげもなく堂々と言ってやるのだ。
「トモダチなんだから、当たり前!」と。
誰になんと思われてもいい。気が違っていると思われても構わない。
昨夜の女や、宝石店の販売員、その他大勢の人にどう思われるかよりも、大事なことは目の前にある。
大事なひとは、目の前にいる。
この不器用で、素直じゃなくて、可愛げがなくて、そしてとんでもなく可愛いトモダチ――〝クラウド〟のことを、
少なくとも今この瞬間は、何よりも、誰よりも、大事にしたいのだ。
仲が良すぎるトモダチ、ぐらいのザックラも好きです。(2016.04.11 C-brand/ MOCOCO)